<非破壊検査、渦電流探傷法とは?>
工場で作った製品や、トンネル・橋といった建造物の検査は一般的に非破壊検査と呼ばれている方法が使われています。これは外観からは分からない内部で発生した傷を、モノを壊さずに検査する方法です。これにより、製品であれば品質向上につなげることが可能であり、トンネルや橋であればピンポイントで傷のある場所を見つけることが出来ます。非破壊検査に使われている手法は実に様々で、超音波探傷(UT)、放射線検査(RT)、磁粉探傷(MT)、渦電流探傷(ET)、浸透検査(PT)など、検査する対象によって最適な検査手法を選ぶ必要があります。後藤研究室では数ある検査手法の中で電磁気を使った非破壊検査手法の研究をしています。特に、今回は渦電流探傷試験について解説をしたいと思います。高校物理で勉強する「電磁誘導」や、「誘導起電力」の知識があれば十分理解できると思います。
渦電流発生の原理
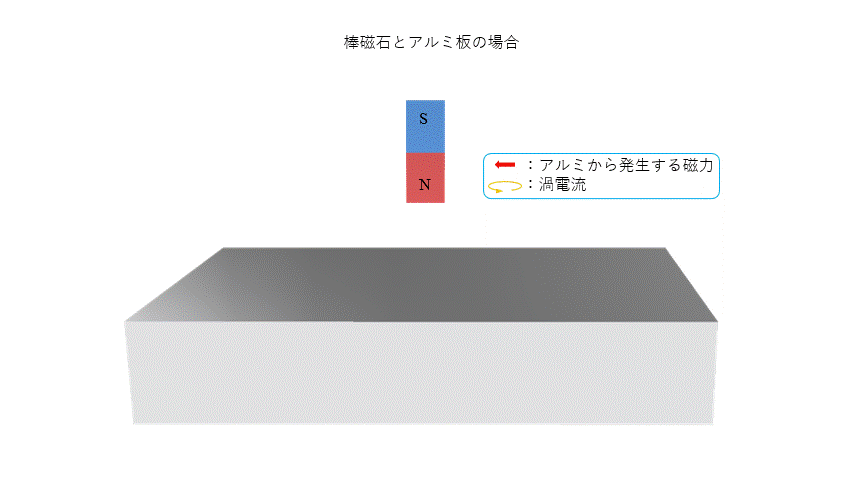
高校物理の教科書でアラゴの円盤や、アルミパイプの中に磁石を入れるとゆっくり落下する現象を勉強するはずです。ここでキーワードとなるのが渦電流です。まずはアルミの板と、棒磁石で考えてみます。アルミ板に棒磁石を近づけると、磁界を妨げる方向にアルミ板から磁界が発生します。磁界が発生すると、アルミ板に渦電流が発生します。この渦電流の向きは「右ネジの法則」に則り決定します。棒磁石を止めると、磁界の変化が無くなり渦電流も発生しなくなります。さて、この状況で磁石を上下に動かしたらどうなるでしょうか?アルミ板に通過している棒磁石の磁力が絶えず変化していますね。これによって渦電流も向きを変えながら絶えず発生し続けます。
棒磁石を電磁石へそして、交流を流すと…
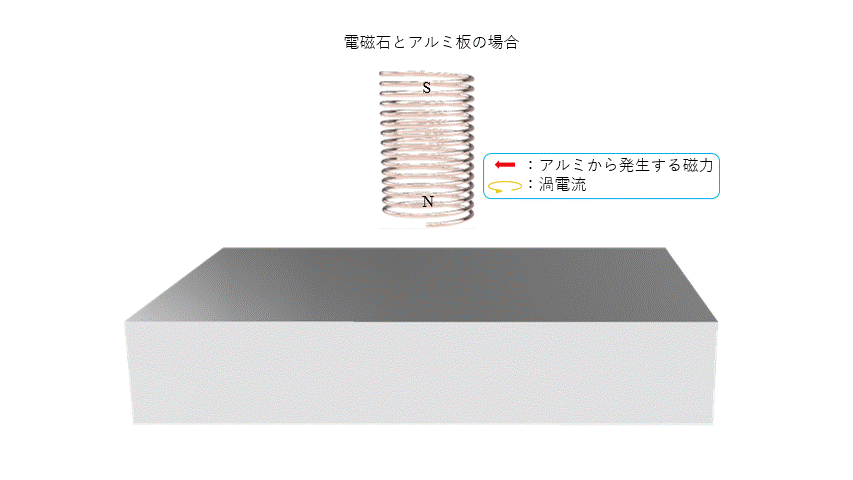
先ほどまでは棒磁石で考えていましたが、今度は電磁石(空芯コイル)に置き換えてみましょう。銅線を巻いてコイルにして、直流の電気を流すと棒磁石と同じふるまいを見せます。上述と同じように、電磁石を上下させると同じように渦電流が発生します。さて、ここで電磁石に流している電流を直流から交流へ変えてみましょう。すると、電磁石は交流の周波数に合わせてN極とS極を反転させるようになります。この状態で、アルミ板の上に電磁石を置いてみます。すると、磁石を動かしていないのにアルミ板の中に渦電流が発生するようになります。これは、電磁石の磁界が常に変化している事が要因です。そのため、アルミ板から発生する電磁石の磁界を打ち消そうとする磁界も常に変化します。よって、渦電流も常に発生するようになるわけです。これにより、電磁石とアルミ板の距離を一定に保つことが出来るようになり、アルミ板の中に発生する渦電流は常に同じ大きさであることも重要です。
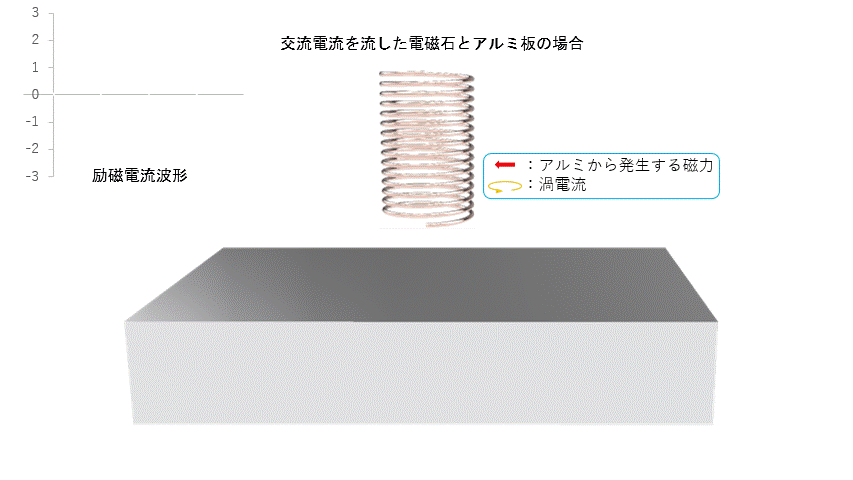
渦電流探傷法へ
 さて、最後にこの原理を渦電流探傷法へ応用しましょう。外からは見えない内部に傷が発生したアルミ板を用意します。これに先ほどの交流電流を流した電磁石を傷の方へ近づけていきます。すると、渦電流は傷を避けるように迂回をします。そのため、きれいに渦を描いていた渦電流は、歪んだ形を描くようになります。この渦電流の歪み具合を測定することで、傷の大きさや深さを検査することが出来ます。これが渦電流探傷法の基本的な原理です。実際に渦電流の変化を検出するためにはブリッジ回路などを使って、インピーダンスの変化を検出する必要がありますが、ここでは割愛します。
さて、最後にこの原理を渦電流探傷法へ応用しましょう。外からは見えない内部に傷が発生したアルミ板を用意します。これに先ほどの交流電流を流した電磁石を傷の方へ近づけていきます。すると、渦電流は傷を避けるように迂回をします。そのため、きれいに渦を描いていた渦電流は、歪んだ形を描くようになります。この渦電流の歪み具合を測定することで、傷の大きさや深さを検査することが出来ます。これが渦電流探傷法の基本的な原理です。実際に渦電流の変化を検出するためにはブリッジ回路などを使って、インピーダンスの変化を検出する必要がありますが、ここでは割愛します。
〈執筆:丹羽〉
詳細次へ